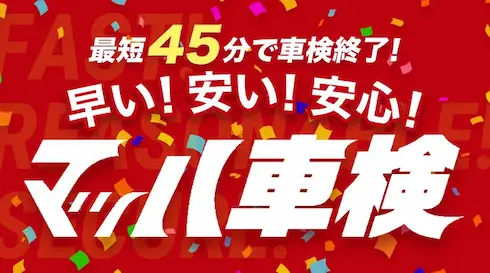軽自動車を8ナンバーとして登録することで、税金や車検の頻度、維持費の面で多くのメリットが得られることをご存じでしょうか。8ナンバーには厳格な構造条件や必要書類、登録手続きの理解が欠かせません。
本記事では、「軽自動車 8ナンバー 条件」に関心のある方に向けて、具体的な取得条件、構造要件、必要書類、さらにはメリットとデメリットまで分かりやすく解説します。これから8ナンバー化を検討している方にとって、必見の内容です。
軽自動車の8ナンバーの条件とは?

軽自動車の8ナンバーがどんなものか、その種類や普通車との違い、ナンバープレートの色まで基本的なことを紹介します。
・8ナンバーとは
・8ナンバーは4種類ある
・普通車の8ナンバーとの違い
・8ナンバーのナンバープレートの色は?
8ナンバーとは
「8ナンバー」とは、特別な目的のために作られた車に付けられるナンバープレートの分類番号のことです。普通の車は、人を乗せたり荷物を運んだりすることが目的ですが、8ナンバーの車はこれに当てはまらない車を指しています。
例えば、パトカーや消防車、給水車などが8ナンバーの代表例です。さらに最近では軽キャンピングカーのように、個人的なレジャーで使う車も8ナンバーに分類されることが増えています。ナンバープレートの地名の右側にある3桁の数字が「8」から始まる数字であれば、その車が特殊用途自動車だということが分かります。
8ナンバーは4種類ある
特殊用途自動車は、その主な使い方によって大きく4つの種類に分けられます。
| 種類 | 用途 | 例 |
| 緊急車両 | 人の命を救う、災害時に活躍する | 救急車、消防車、パトカー |
| 特殊事業者 | 公共サービスや特定の仕事で使う |
ゴミ収集車、郵便車、教習車 |
| 介護・特殊作業・その他の使用目的者 | 介護や特殊な作業をする | 車いす移動車、クレーン車、高所作業者 |
| キャンプ又は宣伝活動車 | キャンプや宣伝活動に使う | キャンピングカー、宣伝カー |
これらの分類は、国が定めた細かなルールに基づいていて、8ナンバーを取得するには、ただ「特殊な設備がある」だけではありません。
その設備がどの用途に当てはまるか、そしてその用途に必要な構造の条件を満たしているかが重要になります。
普通車の8ナンバーとの違い
8ナンバーは、軽自動車にも普通車にもありますが、一番の違いはその車が「軽自動車なのか普通車なのか」といった違いで、特別な目的をもった車に付けられる番号であることは共通しています。
また、8ナンバーの車は新車登録した車両でも、2年後に車検を受けなくてはいけません。これは、普通車・軽自動車どちらにも共通しているポイントです。
普通車も軽自動車も、新車登録してから最初の車検は3年後であることから、8ナンバーに登録すると1年早まることになります。
8ナンバーのナンバープレートの色は?
軽自動車の8ナンバーのナンバープレートは、黄色い背景に黒い文字です。これは普通の軽自動車と同じ色で、分類番号の頭が「8」であることで、特別な目的の車だとわかります。
一方、普通車の8ナンバーのナンバープレートは、白い背景に緑の文字です。
もし、軽自動車を改造してキャンピングカーにした場合でも、車の幅が軽自動車のルール(最大1.48m)を超えてしまうと、たとえエンジンの排気量が660ccのままでも普通車として扱われることになり、「白い8ナンバー」が付けられます。
ナンバープレートの色は、その車が軽自動車のルールに収まっているか、それとも普通自動車として扱われるかを示す目印になります。軽自動車のサイズを超えると、税金や保険、高速道路の料金なども普通車のルールが適用されるので、改造を考える際には注意が必要です。
軽自動車で8ナンバーを取得するための条件

軽自動車で8ナンバーを取得するために、どんな条件を満たし、どんな手続きが必要なのかを説明します。
・構造要件を満たす
・必要書類を揃えて構造変更の手続きをする
・ナンバープレートを付け替える
構造要件を満たす
軽自動車を8ナンバー登録するには、特定の構造的設備を備えていなければなりません。特にキャンピングカーの場合、「就寝」「炊事」「水道」などの設備が必要であり、加えて荷室の一定面積も求められます。以下で具体的な条件を見ていきましょう。
就寝設備
就寝設備は、車内に大人が横になって休めるスペースが常設されていることが要件です。折りたたみ式ベッドやマットレス、寝台として使えるシートアレンジが可能なものも含まれますが、一時的な仮設ではなく、恒常的に就寝可能である必要があります。
また、寝るためのスペースが確保されていても、その広さが足りない場合は認可されません。一般的には、成人1人あたり1.8m以上の就寝スペースが必要とされ、複数人対応の場合は人数に応じた拡張性が求められます。
水道設備
水道設備も8ナンバー登録には欠かせません。具体的には、給水タンク、排水タンク、シンク、蛇口などの設置が必要です。簡易ポンプ式の蛇口や、足踏み式の給水装置でも構いませんが、明確に「水を使用するための設備」として機能することが重要です。
また、給排水の配管がしっかりと取り付けられており、車検時に稼働状態が確認できることも求められます。
炊事設備
炊事設備には、ガスコンロまたは電気コンロといった調理機器が常設されている必要があります。ポータブルなキャンプ用バーナーなどでは認可が下りないことが多く、固定されたコンロや調理台が必要です。
さらに、換気扇や火災予防装置、遮熱板の設置も求められるケースがあり、安全対策が十分かどうかも審査対象となります。炊事スペースの耐久性や配置も構造要件の一部です。
面積
軽自動車の荷室内に設ける生活スペースには、一定以上の面積が求められます。一般的には床面積で2平方メートル以上が目安とされており、その中に就寝・炊事・水道の設備が機能的にレイアウトされていることが必要です。
また、頭上空間の確保も重要で、最低でも1.2m程度の天井高が推奨されます。設備のサイズやレイアウトに無理がある場合、検査に通らないことがあります。
必要書類を揃えて構造変更の手続きをする
軽自動車を8ナンバーにするための手続きは、「軽自動車検査協会」という場所で行います。この手続きは、普通の車検よりも少し厳しく、「書類の審査」と「実際の車の検査」の2段階で行われることが多いです 。
なお、手続きには、以下の書類が必要です 。これらの書類は、軽自動車検査協会の窓口でもらえたり、インターネットからダウンロードできたりします。
自動車検査証(車検証)
車検証は現在の登録情報を確認するために不可欠な書類です。構造変更の申請では、この車検証を元に車両情報が照合され、変更点が正確に記載されることになります。
申請時には原本を提示する必要があるため、事前に紛失していないかを確認しておきましょう。
点検整備記録簿
点検整備記録簿は、直近の整備履歴や点検状況を示す書類です。特に改造によって変更された箇所の安全性確認や、走行に問題がないかを判断する材料となります。構造変更に伴う点検内容を記録しておくことが望ましいです。
自動車重量税納付書
構造変更後の登録時には、自動車重量税の納付が必要です。納付書はその証明となるため、手続き時に提出する必要があります。軽自動車の場合、税額は比較的少額ですが、支払証明を必ず準備しましょう。
自動車損害賠償責任保険証明書
通称「自賠責保険」の証明書で、公道を走行するすべての自動車に義務づけられています。変更登録時にも、保険が有効であることの確認が必要です。保険期間中であることが条件となります。
軽自動車検査票
検査票は、構造変更時の検査記録を取るために必要です。検査協会で入手可能で、当日の構造確認検査時に使用されます。書類不備があると検査自体が受けられないため、事前記入を済ませておくとスムーズです。
自動車検査証記入申請書(軽第2号様式
)
こちらは変更事項を記載するための申請書で、軽自動車専用の第2号様式を使用します。検査協会窓口で取得可能で、構造変更や用途変更に関する情報を詳細に記入します。記載ミスには注意が必要です。
申請審査書
審査書は、提出した内容や検査結果を記録する書類で、申請プロセスの一部として必要です。これにより、構造変更の記録と承認が正式に行われます。窓口で書き方の説明を受けることもできます。
その他
申請内容によっては、以下の書類が追加で必要になります
- 事業用自動車等連絡書:黒ナンバーで登録する際に必要
- 申請依頼書(委任状):代理人が申請する場合に必要
- 改造概要書・写真資料:改造前後の車両写真と改造内容の記録
とくに、キャンピングカーとして登録する場合は、構造図やレイアウト図などの技術資料が求められるケースもあり、事前の準備が鍵となります。
ナンバープレートを付け替える
構造変更の手続きが終わり、新しい車検証がもらえたら、最後にナンバープレートを交換します 。
軽自動車検査協会の中にあるナンバー交付窓口で、古いナンバープレートを返して、新しい8ナンバープレートを買って車に取り付けます。新しいナンバープレートの代金は別途かかります 。
軽自動車の8ナンバーのメリット

軽自動車の8ナンバーを持つことの、メリットを紹介します。税金や高速道路の料金、車検の頻度など、車を維持するうえでお得になる点があります。
・税金を抑えられる
・高速道路の利用料金が安い
・車検の頻度が下がる
税金を抑えられる
軽自動車を8ナンバーに登録すると、税金面でいくつかお得になる可能性があります。
自動車税
軽自動車の8ナンバーは、普通の軽乗用車(5ナンバー)と比べて、自動車税が安くなる場合があります。例えば、地域によっては8ナンバーの軽キャンピングカーを「荷物を運ぶ車」として扱い、普通の軽乗用車が年間10,800円の自動車税を支払うのに対し、8ナンバーの軽キャンピングカーは5,000円に減額されます。
ただし、この税金の安さは全国どこでも同じではありません。軽自動車は国ではなく自治体によって管理されている車であるため、住んでいる自治体によって税額が少し異なる場合があります。
このことから、8ナンバー登録を考える際は、必ずお住まいの自治体の税金のルールを確認しておくことが重要です。
自賠責保険料
8ナンバーでも軽自動車として登録されている限り、保険料は軽自動車基準が適用されます。2025年現在、自家用軽自動車の自賠責保険料(24ヶ月)は約19,730円です。
一方、事業用軽自動車では24ヶ月で約25,000円とやや高くなりますが、それでも普通車の商用車と比べれば安く済みます。保険料の差は用途区分と登録形態によって変動するため、用途登録の確認が重要です。
高速道路の利用料金が安い
軽自動車の8ナンバーの車、特に軽キャンピングカーは、高速道路の料金区分では「軽自動車」として扱われます。そのため、普通の軽自動車と同じ料金で高速道路を利用でき、休日割引や深夜割引なども適用されます。
これは、遠出をすることが多いキャンピングカーの利用者にとって、とても大きなメリットです。車体が大きくなるキャンピングカーでも、軽自動車として扱われることで、普通車と比べて高速道路の料金が1回あたり1,000円以上安くなることもあり、長距離移動の費用を大きく抑えることができます 。
車検の頻度が下がる
8ナンバーに登録された車の車検は、新しく登録するときも、その後も、2年ごとに受けることになっています 。
この2年ごとの車検サイクルは、特定の種類の車と比べると大きなメリットになります。たとえば、荷物を運ぶ車(1ナンバーや4ナンバー)は、通常毎年車検を受けなければなりません。
これらの車を8ナンバーに構造変更すると、車検の頻度を年1から2年に1回に減らすことができ、それに伴う費用や手間を減らせます。
ただし、「車検の頻度が下がる」というメリットは、元の車の車種によって変わります。普通の軽乗用車(5ナンバー)も、新車登録から最初の3年後、その後は2年ごとになるので 、軽乗用車から8ナンバーに改造する場合、車検の頻度自体はあまり変わりません。むしろ、最初の車検が3年から2年に早まるという点で、少しデメリットになる可能性もあります 。なので、このメリットは、改造する前の車が荷物を運ぶ車だった場合に特に大きいと覚えておきましょう。
軽自動車の8ナンバーのデメリット
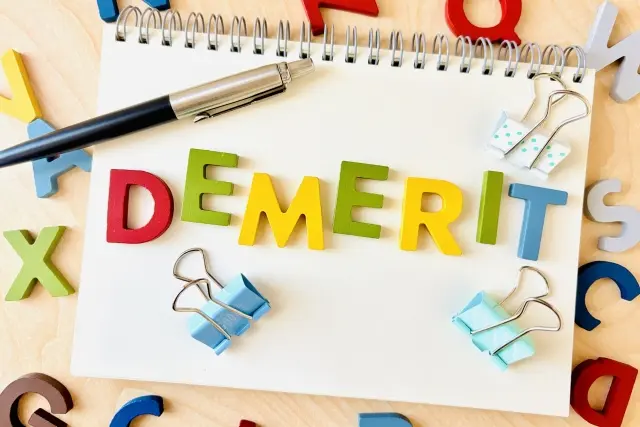
軽自動車の8ナンバーを持つことのデメリットを紹介します。自賠責保険料、任意保険の加入、整備費用など、注意すべき点があります。
・自賠責保険が高くなる
・人気保険の加入が難しい場合がある
・整備費用がかかる
自賠責保険料が高くなる
もし、キャンピングカーなど軽自動車をカスタマイズして8ナンバー登録する場合、軽自動車の規格を超えてしまうとそもそも軽自動車の恩恵が受けられなくなってしまいます。普通乗用車だと自賠責保険料が高くなってしまうため、注意が必要です。
また、改造内容によっては車両重量が増加し、それに伴い保険区分が変更される可能性もあります。事前に保険会社へ登録区分と改造内容を伝え、保険料の試算をしておくと安心です。
任意保険の加入が難しい場合がある
8ナンバーの車、特に軽キャンピングカーのような特別な構造を持つ車の場合、任意保険に入りにくい、または選べる保険会社が限られるというデメリットがあります。
- 8ナンバーの車は特殊なため、保険会社が個別にリスクを評価して保険料を計算する必要があります 。これは保険会社にとって手間がかかり、リスクが高いと判断されやすい傾向があります。
- その結果、8ナンバーの車の任意保険を取り扱っている保険会社が少ないのが現状です 。特にインターネットで申し込むタイプの自動車保険では対応できない可能性が高く、保険代理店を通して申し込むタイプの自動車保険を選ぶ必要があるかもしれません 。
- 国が8ナンバーの取得条件を緩和して、特定の車の普及を後押ししている一方で、保険業界の対応が追いついていない状況が見られます。万が一の事故の際に困らないよう、任意保険の加入については、事前にしっかりと確認しておくことがとても大切です。
整備費用がかかる
8ナンバーを取得するためには、車に寝る場所、水を使う設備、料理をする設備などの特別な設備を取り付ける必要があります 。これらの設備を取り付ける費用に加えて、その後も設備を維持したり、修理したりするのにお金がかかります。
特別な設備は、普通の車の部品とは違う専門的な知識や技術が必要になることが多く、結果として整備費用が高くなる可能性があります 。これは、8ナンバーの車を所有する上で見落としがちな費用なので、長く使うことを考えて、維持費も考慮に入れておく必要があります。
軽自動車の8ナンバーの条件に関するご相談は軽の森へ!
軽自動車で8ナンバーを取得するには、複雑な構造要件や細かい書類手続き、登録変更の知識が求められます。一見すると難解に思えるかもしれませんが、専門知識をもつプロのサポートを受けることで、スムーズかつ確実に登録が可能になります。
「軽の森」では、8ナンバー登録に関するご相談や構造変更サポート、書類作成代行などを実施しています。豊富な経験と実績を持つスタッフが、ユーザー様一人ひとりの目的に合わせた最適な提案を行います。まずはお気軽にお問い合わせください。