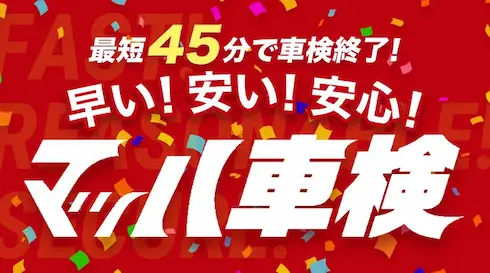軽自動車は維持費が安く、家計に優しい車として幅広い世代に人気です。
特に注目されるのが「保険料の安さ」で、普通車よりも年間保険料が大幅に低くなる傾向があります。
本記事では、軽自動車の保険料の相場や決定要因、2025年から導入される料率クラスの改定内容とその理由、そして保険料を抑えるための具体策まで網羅的に解説します。
軽自動車の保険料の相場は?

軽自動車の年間保険料の相場は約49,511円であると報告されています。
これは、損害保険料率算出機構が公表している「自動車保険の概況2023年度(p.102)」のデータに基づいた金額です。
参考までに、同機構が示す普通車(自家用乗用車)の相場は約72,327円、小型車(自家用小型乗用車)は約54,806円とされており、軽自動車は最も保険料が安い車種区分であることがわかります。これにより、保険会社にとってもリスクの低い車両とされ、料率も有利に設定されているのです。
軽自動車は費用面でも優れた選択肢といえるでしょう。
軽自動車の保険料が安い理由
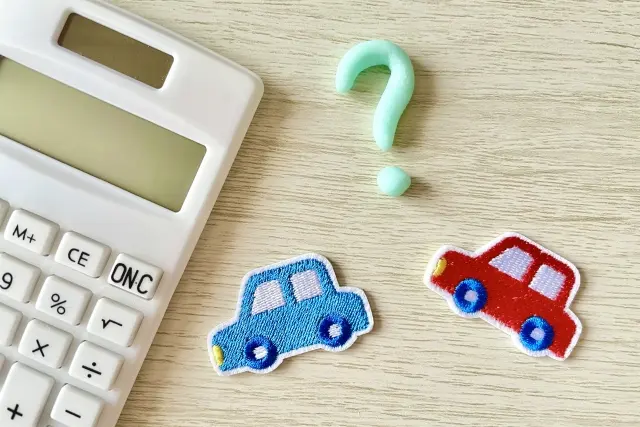
軽自動車の保険料が安いのは、事故発生率が低く、車両修理費など保険会社が支払う保険金の額が少ないためです。これにより、各保険会社は軽自動車に対して低めの料率を設定できるのです。
事故率が低いから
軽自動車は主に近距離での使用が多く、走行スピードも比較的低いため、重大事故につながるリスクが少ないとされています。
たとえば、都市部では買い物や送迎など日常的な用途で利用されることが多く、一般道路での軽微な接触事故が主です。このような背景から、軽自動車の事故発生率は普通車よりも低くなる傾向にあります。
事故率の低さは、保険会社にとって支払いリスクの軽減を意味し、料率の設定にも大きく影響します。
結果として、契約者にとっては保険料が安くなるメリットが生まれます。
保険金支払額が少ないから
軽自動車は車両価格が比較的安価であるため、事故発生時に必要となる修理費や保険金の支払額も抑えられる傾向にあります。
たとえば、車両保険を付けた場合でも、同じ事故内容であっても普通車より支払額が低く済むケースが多いのです。また、部品価格も軽自動車の方が安く、修理工数も少なく済むことが多いため、保険会社にとってはトータルの支払いリスクが少なくて済みます。
こうした背景により、保険料の算出に用いられる料率も低くなり、契約者には経済的なメリットが還元される仕組みとなっています。
軽自動車の保険料が決まる要因

軽自動車の保険料は、単に車種や年式によるだけでなく、契約者の属性や運転歴、補償範囲など、複数の要因によって決定されます。
代表的な要因を以下に整理しました。
- ・運転する人の年齢や範囲
- ・運転免許証の色
- ・事故歴
- ・使用目的
- ・補償内容
運転する人の年齢や範囲
保険契約時に設定する運転者の「年齢条件」や「範囲」は、保険料に大きく影響します。
たとえば、「30歳以上補償」や「本人・配偶者限定」などに設定すれば、リスクが限定されるため料率が下がり、保険料は安くなります。逆に、「全年齢対象」や「誰でも運転可」など広範な設定にするとリスクが高まるため、保険料も高額になります。
保険会社は統計的な事故データをもとに、年齢や範囲ごとの料率を設定しているためです。
運転免許証の色
免許証の色は「事故リスク」を判断する一つの指標として、保険会社が評価対象にしています。
ゴールド免許の所有者は、過去5年間に重大違反や事故がなく、安全運転を継続しているとみなされます。そのため、保険会社の多くはゴールド免許所持者に対して割引制度を導入しています。
逆に、ブルー免許の人や違反歴がある人は、リスクが高いと見なされ、保険料がやや高く設定されることがあります。
事故歴
過去の事故歴は、保険会社にとってリスク判断の重要な要素です。
自動車保険には「ノンフリート等級制度」が採用されており、事故の有無によって等級が上下します。たとえば、無事故であれば1年ごとに等級が上がり、割引率が増加。事故があれば等級が下がり、翌年からの保険料が上がる仕組みです。
事故歴が多いと、料率が悪化し、結果的に保険料が大幅に上昇するリスクがあります。
使用目的
保険契約時には車の「使用目的」を申告する必要があり、これは保険料に直接影響します。
主な区分は「日常・レジャー」「通勤・通学」「業務使用」の3つです。日常使用であれば事故の頻度が少なく、リスクが低いため保険料は安価になります。一方、通勤や業務での使用は走行距離が長くなる傾向があり、事故のリスクが高まるため、料率が上がり保険料が高く設定されることがあります。
補償内容
補償内容は保険料に最も大きく影響を与える要素の一つです。
たとえば、対人・対物賠償を「無制限」に設定するか、「5000万円」などの限度付きにするかで大きく差が出ます。また、車両保険を付けるか否か、特約をどれだけ付帯するかによっても料率が変動します。
必要な補償だけを選び、不要なものを削除することで、保険料を最適化することが可能になります。
軽自動車の保険料は2025年から値上がりする?
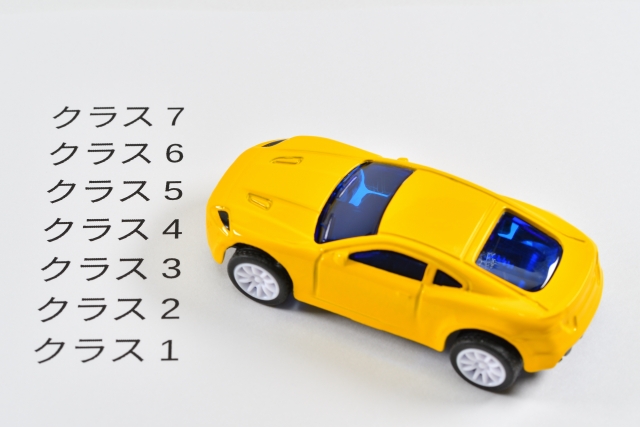
2025年1月より、軽自動車に対する「型式別料率クラス」の適用範囲が従来の1区分から7段階に細分化されます。これにより、一部の軽自動車で保険料が上がる可能性があります。
制度改定の内容を詳しく解説します。
型式別料率クラスとは
型式別料率クラスとは、車両ごとの事故発生状況や保険金支払い実績などの統計に基づき、保険会社が設定するリスク評価の基準です。
これまで普通車にはすでに導入されており、保険料算出の大きな要素となってきました。自動車は同じように見えても、型式(=メーカー・車種・グレードなど)ごとに事故率や修理費用が異なり、それを数値化してリスクを明示するのがこの制度の役割です。
料率クラスの数値が高いほどリスクが高いと評価され、結果として保険料も高くなる仕組みです。
2025年1月から7クラスに拡大
これまで軽自動車においては、型式別料率クラスは「1クラス」で一律に取り扱われてきましたが、2025年1月より「最大7クラス」に細分化されることが正式に発表されました。
これは、軽自動車の台数・事故件数が増加し、統計的に有意な差が見られるようになったためです。これにより、車種や型式によって保険料に差がつくことになります。
たとえば、事故率の高い車種では保険料が上がり、事故率の低い車種では逆に下がる可能性もあります。
7クラスに細分化された理由
細分化の背景には、近年の軽自動車の多様化と、それに伴う事故データの蓄積があります。
以前は軽自動車は「一律のリスク」と見なされていましたが、実際には車種や使用状況により事故発生率や保険金支払い額に明確な差が出てきています。損害保険料率算出機構は、こうした差異を公平に反映するため、料率クラスを7段階に分ける制度改革を決定しました。
これにより、リスクの高い車種と低い車種で、より公正な保険料設定が実現されるのです。
型式別料率クラスのモデル例
例えば、人気のある軽自動車「N-BOX」や「タント」などは販売台数が多く、事故や修理データが豊富に蓄積されています。
仮にN-BOXが「対人3・対物4・傷害2・車両3」というようなクラスに分類されれば、対物と車両のリスクが平均よりやや高いと評価されます。この場合、従来の一律料率よりも保険料がやや高くなる可能性があります。
逆に、スズキ・アルトなど比較的事故件数が少ない車種は、クラスが低く設定され、保険料が抑えられることもあります。
型式別料率クラスを調べる方法
自分の軽自動車がどの料率クラスに該当するかを確認するには、保険会社のウェブサイトや損害保険料率算出機構の公開データを参照する方法があります。
多くの保険会社では、契約手続き画面や見積もりシミュレーションの際に、車両型式を入力することで自動的に料率クラスを反映させた保険料が提示されます。
2025年以降はこのクラス差が大きな判断材料となるため、車を購入する前や保険契約前に必ず確認するようにしましょう。
軽自動車の保険料を抑えるポイント
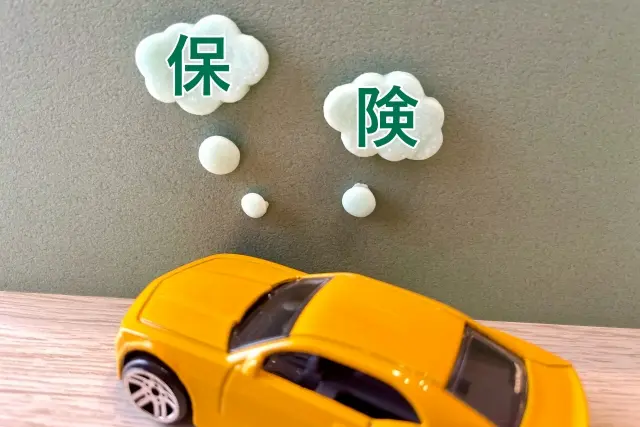
保険料をできるだけ安くしたい場合は、契約内容や補償範囲の見直しが効果的です。
以下に、すぐに実践できる7つの節約ポイントを具体的に紹介します。
7つの節約ポイント
対象となる運転者や年齢を限定する
契約時に「運転者限定特約」や「年齢条件特約」を設定することで、大幅に保険料を削減することができます。
たとえば「本人限定+35歳以上補償」に設定すれば、事故リスクが著しく下がるため、保険会社は低料率を適用できます。逆に、全年齢補償・誰でも運転可という設定では、料率が上がり、保険料が高くなるので注意が必要です。
家族構成や使用目的を考慮して、運転者範囲の設定を見直しましょう。
補償範囲を見直す
過剰な補償をつけていないか定期的にチェックすることが重要です。
たとえば、車両保険に「一般条件」を付けていると高額になりがちですが、「エコノミー+限定A」などに変更すれば保険料は抑えられます。また、「弁護士費用特約」や「ロードサービス特約」なども必要に応じて選択しましょう。
全てを網羅するのではなく、自分の生活スタイルや車の使用頻度に合わせて、無駄のない補償を選ぶことが節約のカギです。
免責金額を再設定する
車両保険を付けている場合、免責金額(自己負担額)を高く設定することで保険料を下げることができます。
例えば、免責を「5万円」に設定するよりも「10万円」にした方が、保険料は安くなります。ただし、事故時にはこの自己負担額を支払う必要があるため、手元資金とのバランスを考慮する必要があります。小さな事故に備えるよりも、大きな損害に備えたい人にとって有効な手段です。
月払い設定を年払い設定に変更する
保険料を月払いに設定すると、事務手数料や割増が発生することがあります。
一方、年払いに設定することで、これらの手数料が発生せず、結果として保険料が安く済みます。また、保険会社によっては年払いにすることで数パーセントの割引を受けられるケースもあります。
まとまった出費が可能であれば、ぜひ年払いを選択し、トータルコストを抑えるようにしましょう。
ダイレクト型自動車保険へ切り替える
代理店型よりも「ダイレクト型(通販型)」の自動車保険は、販売コストが少ないため、保険料が割安です。
インターネットで契約から支払いまで完結できるため、人件費や事務手数料が抑えられています。補償内容も自由にカスタマイズでき、サイト上で簡単に比較・見積もりが可能です。
サポート体制が整っている会社も多く、事故対応もオンラインで迅速に行われます。コスト重視の方には特におすすめです。
保険会社を比較する
同じ補償内容でも、保険会社によって保険料に差があります。各社が独自に設定する「割引制度」や「事故対応サービス」、「車両修理ネットワーク」などの違いを確認することが大切です。
インターネット上には複数社を比較できるランキングサイトや比較サイトもあるため、積極的に活用しましょう。契約前には必ず複数の保険会社から見積もりを取り、価格とサービスのバランスを確認することが重要です。
型式別料率クラスの数字が低い軽自動車を選ぶ
新車購入時に「型式別料率クラス」が低い車種を選ぶことも、長期的に保険料を抑えるポイントになります。
料率クラスは「対人・対物・傷害・車両」の4項目に分かれ、それぞれ1~17の数字でリスクを表します。軽自動車でも、車種によっては高いクラスに分類されることもあるため注意が必要です。
購入前に各保険会社のサイトや資料で該当車種の料率クラスを確認しておくと、より賢い選択が可能になります。
軽自動車の保険料に関するご相談は軽の森へ!
本記事では、軽自動車の保険料に関する相場や料率、制度変更、保険会社の比較方法まで幅広く解説しました。
万一の事故に備えつつ、保険料を無理なく抑えるためには、正しい情報と賢い選択が不可欠です。また、万が一の紛失や盗難などで車検証の再発行が必要な場合もあります。
その際は、「軽の森」のような信頼できるサービス会社に相談することで、スムーズな手続きを受けることができます。安心・確実なサポートを受けるためにも、信頼性の高いサービスを活用しましょう。