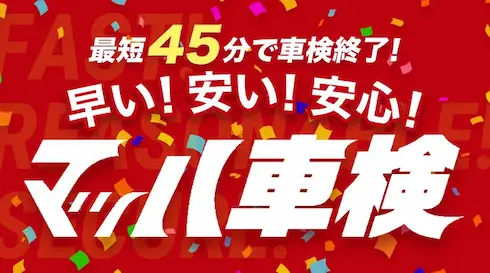所有している軽自動車のタイヤのサイズが何なのか、分からないという方も多いのではないでしょうか。普段、車に装着しているタイヤのサイズを気にする方は少なく、タイヤの買い替えを検討するまで知らなくても当然のことです。
しかし、タイヤのサイズをよく把握しておかないとタイヤの購入時にサイズ間違いをしてしまったり、走行に影響が及んでしまったりしてしまいます。
そこでこの記事では、軽自動車のタイヤサイズについて人気モデルのタイヤサイズ一覧や、軽自動車のタイヤサイズの調べ方を紹介します。タイヤサイズをわざと変更するメリットとデメリットについてもまとめているので、軽自動車のタイヤサイズでお困りの方は、ぜひ参考にしてみてください。
軽自動車のタイヤのサイズは?

軽自動車のタイヤサイズは、走行距離や燃費、安全性に直結する重要なポイントで、車種やグレードによって異なります。
サイズを確認するには、車両の取り扱い説明書や運転席側のドア付近のラベル、またはタイヤの側面に記載された情報をチェックします。
ここからは、軽自動車の主なタイヤサイズや、数字・アルファベットの意味について見ていきましょう。
軽自動車の主要なタイヤサイズ
軽自動車に多く使われているタイヤサイズには、「145/80R13」や「155/65R13」、「155/65R14」、「165/55R15」などがあります。
一般的に13~15インチのホイール径が主流で、車のタイプや年式、グレードによっても異なります。燃費を重視したモデルでは、13インチが多く、スポーティな仕様では15インチが採用されることもあります。
サイズを変更する際は、スピードメーターの誤差や車体への干渉に注意が必要です。純正サイズの維持がもっとも安心・安全とされ、メーカーが推奨するサイズの範囲内で選ぶことが重要です。
数字やアルファベットの意味
タイヤの側面に記載されている「155/65R14」などの表記には、それぞれ意味があります。「155」はタイヤ幅(mm)、「65」は扁平率(断面の高さ÷幅×100)を表しています。
また。「R」はラジアル構造、「14」はホイールの直径(インチ)です。
その他にも「82S」などの表記には、荷重指数(ロードインデックス)と速度記号が含まれ、適合性の判断材料になります。
これらの情報を理解することで、適切なタイヤ選びができ、性能や安全性を確保できるでしょう。タイヤ交換やカスタムを行う際には、これらの数値を正確に読み取ることが大切です。
【メーカー別】軽自動車の人気モデルのタイヤサイズ一覧

軽自動車はメーカーによって装着されるタイヤサイズに特徴があります。ここでは、主要メーカーであるスズキやダイハツ、日産、ホンダの人気モデルに採用されている代表的なタイヤサイズを紹介します。
同じ車種でも年式やグレードでサイズが異なる場合があるため、実際に使用されているタイヤの側面や車両ラベルを確認することが基本です。
純正のタイヤサイズを知ることで、交換時やスタッドレスタイヤを選ぶ際にも役立ちます。安全性を確保するためにも、メーカーの指定サイズを基準に選ぶがポイントです。
スズキ
| 車種 | タイヤサイズ |
| ワゴンR | 155/65R14 |
| アルト | 155/65R14 |
| スペーシア | 155/65R14 |
ダイハツ
| 車種 | タイヤサイズ |
| タント | 155/65R14 |
| ミライース | 155/70R13 |
| ムーヴキャンバス | 155/65R14 |
日産
| 車種 | タイヤサイズ |
| デイズ | 155/65R14 |
| ルークス | 155/65R14 |
| モコ | 145/80R13 |
ホンダ
| 車種 | タイヤサイズ |
| N-BOX | 155/65R14 |
| N-ONE | 155/65R14 |
| N-WGN | 155/65R14 |
軽自動車のタイヤサイズの調べ方
軽自動車のタイヤサイズは車両ごとに異なるため、正確に把握しておくことが重要です。確認方法は主に4つあり、「タイヤの側面」と「運転席側のドア内側のラベル」、「取扱説明書」「メーカーの公式サイト」が代表的です。
これらの情報源から、自分の車に合ったタイヤサイズを調べられるでしょう。違ったサイズを選んでしまうと、安全性や燃費に悪影響を及ぼしてしまうため、必ず情報を照らし合わせて確認することが重要です。
タイヤの側面
もっとも簡単にタイヤサイズを確認できる方法が、装着されているタイヤの側面を見ることです。「155/65R14」などの数字が刻印されており、これがタイヤのサイズを示しています。
ただし、中古車で購入した車の場合、前のオーナーが純正サイズと異なるタイヤに交換している可能性もあるため、この情報だけで判断するのは避けましょう。
ほかの情報源とあわせて確認することで、正確なサイズの把握ができます。
運転席側のドアの内側
運転席側のドアを開けた内側の柱部分には、タイヤサイズや空気圧が記載されたステッカーが貼られているのが一般的です。
この情報はメーカーが推奨する純正サイズであり、信頼性が高いです。前後輪でサイズや空気圧が異なる場合もあるため、表示内容をよく確認することが重要です。
タイヤ交換時にはこのラベルを基準にして選ぶと、車検にも適合しやすく安全性も確保できるでしょう。
メーカーの公式サイト
所有している車のタイヤサイズを調べる方法として、各メーカーの公式サイトも有効です。「車種名+タイヤサイズ」で検索すると、カタログ情報や仕様一覧が掲載されていることが多く、年式やグレードごとのタイヤサイズも確認できます。
とくに中古車や型落ちモデルになっている場合、当時の情報がメーカーサイトで観覧できることもあるため、正確なデータの確認に役立ちます。ネットにはあらゆる情報が広がっていますが、公式サイトであれば信頼性が高いでしょう。
取り扱い説明書
車両に付属する取扱説明書にも、タイヤサイズやタイヤ交換を行う際の注意点が詳しく記載されています。標準装備のタイヤサイズや、オプションタイヤ、適正空気圧などの情報が網羅されており、正確性と網羅性に優れています。
新車購入時に付属していたものが残っていれば、まず確認しておくと安心です。中古車などで説明書がない場合は、メーカーのウェブサイトで電子版を確認できる可能性もあります。
軽自動車のタイヤサイズは変更しても問題ない?
軽自動車のタイヤサイズは変更すること自体は可能ですが、注意点を守らなければ安全性や法令面に問題が生じる可能性があります。見た目や性能を目的としてカスタムも人気ですが、タイヤ外径や荷重指数、車体との干渉といった要素を考慮しないとトラブルの原因になります。
正しくサイズ変更を行うには、基本的な知識と注意点の理解が必要不可欠です。
タイヤサイズの変更自体は可能
タイヤサイズの変更は、基準を守れば合法かつ安全に行うことができます。たとえば、扁平率やホイールサイズを変えて見た目や性能を向上させるカスタムもよく見られます。
しかし、タイヤ外径や幅を大きく変えると、車体に干渉したり走行性能に悪影響を及ぼしたりすることがあります。変更する際は、純正サイズとのバランスや車検適合性を考慮した選択が求められます。
タイヤサイズの変更で起こりうるリスク
タイヤサイズの変更で起こりうるリスクには、以下のようなことがあげられます。
・走行に影響が及ぶ
・車検に通らない
・オドメーターが狂う
ここからは、ひとつずつ詳しく解説します。
走行に影響が及ぶ
タイヤサイズを無理に変更すると、ハンドリングやブレーキ性能に影響がでる場合があります。タイヤが広がりすぎると路面との摩擦が増え、燃費が悪化することも考えられます。
しかし逆に細すぎるとグリップ力が低下して、雨天時のスリップリスクが上がってしまいます。安全で快適な走行を保つには、車の特性に合ったサイズ選びが重要です。
車検に通らない
タイヤサイズが基準を外れると、車検に通らない恐れがあります。とくに車体からタイヤがはみ出していたり、スピードメーターの誤差が基準を超えるなどの状態は不適合となります。
サイズ変更をする場合は、車検制度に適合するかどうかを必ず確認しなければなりません。見た目だけで判断せず、合法性を優先することが大切です。
オドメーターが狂う
タイヤの外径を変更すると、オドメーター(走行距離計)やスピードメーターの表示がずれる場合があります。これはタイヤの回転数が変化するためで、実際よりも多く走行したように表示されるなどの誤差が生じます。
速度表示の誤差が一定以上になると車検も不合格となるため、外径は出来る限り純正に近い値に抑える必要があります。
ポイントを押さえて変更することが大切
タイヤサイズを変更する際は、見た目だけでなく、構造的・法的な条件を十分に理解して選ぶ必要があります。安全性や乗り心地を保ちつつ、基準を外れないようにするためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
外径、リム位置、ロードインデックスに注意しながら、確実に適合するサイズを選ぶことが、トラブルを防ぐ第一歩です。
タイヤの外径は変えない
タイヤの外径(直径)が変わると、メーター誤差や車体干渉などの不具合が発生します。そのため、外径はできるだけ純正サイズと近い値に保つことが基本です。タイヤ幅や扁平率、ホイール径を変更する場合も、トータルの外径が維持されるようにタイヤサイズ早見表などを参考に選定することが重要です。
タイヤ・リムが車体の外にはみ出さない
タイヤやホイールのリムがフェンダー(車体)からはみ出すと、保安基準違反となり車検に通りません。これは外観上の問題だけでなく、走行時の泥ハネや他車への影響を防ぐための規制です。オフセット値を調整することで対応できますが、微調整には専門的な知識が必要となるため、慎重な判断が求められます。
ロードインデックスを下回らない
ロードインデックスは、1本のタイヤが支えられる最大荷重を示す数値です。これが純正よりも低いタイヤを装着すると、荷重に耐えられずタイヤの破損やバーストの原因となることがあります。
カスタム時でも必ず純正と同等以上のロードインデックスを選ぶことが基本で、安全性確保のうえで外せない条件です。
【方法別】軽自動車のタイヤサイズを変更するメリット・デメリット
タイヤサイズの変更には「インチアップ」「インチダウン」「タイヤ幅の変更」などの方法があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。
走行性能や見た目の改善、乗り心地の向上を目的にカスタムされることも多いですが、不適切な変更は安全性や快適性に悪影響を及ぼす可能性があります。目的に応じた変更を選び、バランスを考慮して判断することが大切です。
インチアップ
インチアップとは、ホイールの直径を大きくし、それに合わせて扁平なタイヤを装着する方法です。これにより、見た目がスポーティになり、コーナリング性能の向上が期待できます。
一方で、扁平タイヤは衝撃吸収性が低いため、乗り心地が硬くなりがちです。また、タイヤやホイールの価格も高くなる傾向があります。外径を変えないことを前提に、安全性と走行性能のバランスを考慮して実施すべき変更です。
インチダウン
インチダウンはホイールの直径を小さくし、タイヤの厚み(扁平率)を上げる方法です。乗り心地が柔らかくなり、段差や荒れた路面でも快適に走行できます。
また、タイヤの価格も比較的安価で、スタッドレスタイヤ装着時にもよく選ばれます。ただし、見た目の迫力に欠けたり、操縦安定性がやや低下することもあるため、主に快適性やコスト重視の人に適した方法です。
タイヤ幅の変更
タイヤ幅を広げると、接地面積が増えてグリップ力や安定性が向上します。スポーティな走行や見た目を重視する方に好まれますが、転がり抵抗が増すため燃費が悪化する場合があります。
一方、幅を狭くすると燃費は改善されますが、グリップ力が低下しやすく、滑りやすい路面で不安定になるリスクもあります。車体やホイールを防ぐためにも、適切なサイズ選びが重要です。
軽自動車のタイヤサイズに関するご相談は軽の森へ!
軽自動車のタイヤサイズは車種ごとに決まっており、安全性や快適性に大きく関わります。調べ方はタイヤ側面やドア内側のラベル、取扱い説明書などで簡単に確認でき、サイズ変更もポイントを守れば可能です。
しかし、インチアップや幅の変更にはリスクもあるため、外径や荷重指数などを考慮して選ぶことが重要です。カスタムは見た目だけでなく、安全性と法令順守を前提に行いましょう。
南大阪を拠点とする軽の森では、軽自動車を専門に取り扱っております。今回ご紹介したタイヤサイズに関するお悩みにも関しても全力でサポートさせていただきますので、ぜひお気軽にお問い合わせください!
皆さまからのお問い合わせ・ご予約を心よりお待ちしております。