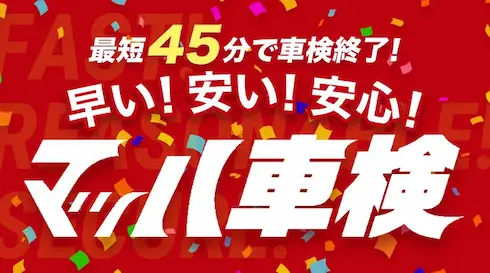自動車のナンバープレートに表示される「5ナンバー」や「4ナンバー」、そして「3ナンバー」。これらの番号には明確な意味があり、車の用途やサイズによって分類されています。特に軽自動車のナンバー制度は、税金や維持費、車検頻度に直結する重要な要素です。
そこでこの記事では、軽自動車の「5ナンバー」とは何か、また4ナンバーや3ナンバーとの違い、さらには変更可能かどうかまでを詳しく解説します。これから軽自動車を購入・登録しようと考えている方、ナンバー制度を持つ方は、ぜひ参考にしてみてください。
軽自動車の5ナンバーとは?
「5ナンバー」とは、自動車のナンバープレートに記載されている分類番号のひとつで、乗用タイプの軽自動車につけられます。
登録時に用途や車体の規格に基づいて付与される番号で、日常的な使用や通勤・買い物など、一般的な使い方をする車に割り当てられることが特徴です。
・5ナンバーは軽自動車の基本ナンバー
・5ナンバーの規格・条件
・代表的な車種
・黒ナンバーとの違い
・最近は7ナンバーもある?
5ナンバーは軽自動車の基本ナンバー
結論からいうと、軽自動車の5ナンバーは「乗用目的の軽自動車」に与えられる標準的なナンバーです。たとえば、ダイハツ・タントやホンダ・N-BOXなど、4人乗りで日常使用が主なモデルにこの番号が付与されます。
5ナンバーの番号部分はナンバープレートの左上にあり、「580」や「581」などの形で表記されます。この「5」から始まる番号が、乗用車であることを示す識別子となります。
つまり、軽自動車でありながらも、貨物用途ではなく「人を運ぶための登録」がなれてれいるということです。
5ナンバーの規格・条件
軽自動車が5ナンバーとして登録されるには、以下のような規格・条件を満たす必要があります。
| 排気量 | 660cc以下 |
| 車両サイズ | 全長3.4m以下、全幅1.48m以下、全高2.0m以下 |
| 乗車定員 | 最大4人まで |
| 用途 | 主に乗用目的 |
これらの条件を満たしていることで「軽自動車」として認められ、さらにその中で貨物用途ではない車両が5ナンバーとして登録されます。なお、登録時には陸運局での検査があり、車両の用途や構造が厳密にチェックされます。
また、ナンバー登録の際には自賠責保険の加入や各種書類(車庫証明など)も必要です。登録をスムーズに行うためには、条件を満たしているかどうかを事前に確認しておくことが重要です。
代表的な車種
5ナンバーが付けられる軽自動車には、次のような人気の車種があります。
| ホンダ・N-BOX | 日本で最も売れている軽自動車。安全装備が充実。 |
 |
|
| ダイハツ・タント | スライドドアが便利で、ファミリー層に人気。 |
 |
|
| スズキ・ワゴンR | 低燃費とコンパクト設計が魅力。 |
 |
|
| 日産・ルークス | 高級感ある内装と快適性が特徴。 |
 |
これらの車種はいずれも乗用目的で設計されており、新車販売時点で5ナンバーが付与されます。価格帯も100万円前半からと手ごろで、日常使いに適した軽自動車です。
黒ナンバーとの違い
黒ナンバーとは「営業用軽貨物自動車」に付けられるナンバーで、5ナンバーとは用途が異なります。具体的には、以下のような違いがあります。
| 比較項目 | 5ナンバー | 黒ナンバー |
| 用途 | 乗用(自家用) | 貨物運送(営業用) |
| プレート色 | 黄色に黒文字 | 黒色に黄色文字 |
| 登録種別 | 自家用軽乗用車 | 営業用軽貨物車 |
| 主な使用者 | 一般家庭・個人 | 宅配業者・運送業者 |
黒ナンバーは営業活動に使う場合、たとえば宅配やデリバリー用に登録する必要があります。そのため、自家用で使う5ナンバーとは明確な違いがあります。
最近は7ナンバーもある?
軽自動車で「7ナンバー」を見かけることもありますが、これは非常に稀なケースで、特定の条件下でのみ付けられます。基本的には普通車に割り当てられる分類であり、軽自動車には原則付きません。ただし、次のようなケースでは例外的に7ナンバーが関係します。
- 福祉車両で改造が加わった軽自動車
- 構造変更により排気量や車体寸法が規格を超えた場合
- 車椅子スロープ等の設備を追加した特殊用途軽自動車
このような軽自動車は、登録内容によっては7ナンバーや8ナンバーの扱いになることがあります。とくに特殊用途としての登録になると「ナンバーの分類番号」が変更されることになります。
ただし、新車購入時に一般的な軽自動車で7ナンバーが与えられることはほとんどなく、ほとんどのケースで5ナンバーか4ナンバーのいずれかになります。
軽自動車の5ナンバーと4ナンバーの違い

軽自動車には、乗用を示す5ナンバーと、貨物用途を示す4ナンバーの2種類が存在します。見た目が似ていても、登録区分やナンバープレートの意味、税金、車検頻度などに大きな違いがあります。
ここからは、両者の規格や税制面での違いを詳しく見ていきます。
・4ナンバーは小型貨物自動車に付けられる
・4ナンバーの規格・条件
・5ナンバーと4ナンバーの税金の違い
・車検頻度の違い
4ナンバーは小型貨物自動車に付けられる
4ナンバーは、軽自動車のなかでも「貨物用途」に使われる車に割り当てられる番号です。具体的には、商用バンや宅配便車両などに多く見られ、荷物の運搬を主な目的とする登録になります。
ナンバープレートの色は黒地に黄色文字で、左上の分類番号は「4」から始まる三桁の数字が記されています。たとえば、スズキ・エブリイやダイハツ・ハイゼットカーゴなどが代表的な4ナンバー軽自動車です。
車種自体は乗用タイプと似ていますが、リアシートの構造や荷室スペースが貨物運搬に適した設計になっています。
4ナンバーの規格・条件
4ナンバーとして登録される軽自動車には、次のような条件があります。
- 排気量:660cc以下(5ナンバーと同じ)
- サイズ:全長3.4m以下、全幅1.48m以下、全高2.0m以下(5ナンバーと同じ)
- 乗車定員:2名または4名
- 荷室スペース:積載スペースが一定の広さを持つこと
さらに、「荷室と座席との仕切りがある」「床面が平坦である」など貨物運搬に適した構造であることが条件です。このような構造的・使用目的の違いにより、登録時の審査や税制上の取り扱いも異なります。
5ナンバーと4ナンバーの税金の違い
5ナンバーと4ナンバーでは、同じ軽自動車でも税金の金額などが異なります。これは、用途の違いによる分類のためです。とくに「軽自動車税」と「自動車重量税」に違いが見られます。
自動車税・軽自動車税
自動車税は市区町村に納める年税で、軽自動車の5ナンバーと4ナンバーで税額が異なります。
| ナンバー区分 | 軽自動車税 |
| 5ナンバー(乗用) | 10,800円 |
| 4ナンバー(貨物) | 5,000~6,000円 |
4ナンバーは商用車として登録されるため、税金が優遇されており、5ナンバーよりも年間コストが抑えられます。事業用として複数台所有する企業にとっては大きな節税効果があります。
自動車重量税
自動車重量税が車検時に国へ納める税金で、こちらも5ナンバーと4ナンバーで金額が異なります。
| ナンバー区分 | 重量税 |
| 5ナンバー | 6,600円 |
| 4ナンバー | 3,300円 |
重量税も貨物用途の4ナンバーは税額が低めに設定されています。ただし、新車登録後13年・18年を経過した車両については、環境負荷の観点から税額が上昇します。したがって、古い軽自動車の場合はこの差が縮まるケースもあります。
車検頻度の違い
5ナンバーと4ナンバーでは、車検の頻度にも違いがあります。
| ナンバー区分 | 初回車検 | 以降 |
| 5ナンバー | 新車登録から3年後 | 2年ごとに車検 |
| 4ナンバー | 新車登録から2年後 | 1年ごとに車検 |
このように、4ナンバーは貨物用途という性質上、車両の安全性確保のため車検頻度が高くなります。そのため、短期間での整備費用や手間がかかるというデメリットがあります。日常使いがメインであれば、5ナンバーの方が維持管理がしやすいと言えるでしょう。
軽自動車の5ナンバーと3ナンバーの違い

軽自動車は基本的に5ナンバーまたは4ナンバーに分類されますが、「3ナンバー」は普通自動車に付けられる番号です。ボディサイズや排気量の違いによって登録の分類が異なり、維持費や車検にも影響があります。ここからは、5ナンバーと3ナンバーの違いを詳しく解説します。
・3ナンバーは普通自動車に付けられる
・5ナンバーの規格・条件
・5ナンバーと3ナンバーの税金の違い
・車検頻度の違い
3ナンバーは普通自動車に付けられる
3ナンバーは「小型車規格を超える普通乗用自動車」に付けられるナンバーです。小型乗用車の基準は、排気量2,000cc以下、全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.0m以下で、どれかひとつでも条件に満たない場合は3ナンバーの対象になります。
ナンバープレートの左上に3から始まる三桁の数字が表示されており、これが3ナンバー車を表します。代表的な3ナンバー車には、トヨタ・アルファードや日産・エルグランドなどのミニバン、スバル・レガシィなどの大型セダンが含まれます。
これらの車両は、快適な居住空間とパワフルな走行性能を持つため、ファミリーユースや長距離移動に適しています。
3ナンバーの規格・条件
3ナンバーとして登録される軽自動車には、次のような条件があります。
- 排気量:2,001cc以上
- サイズ:全長4,701mm以上、全幅1,701mm以上、全高2,001mm以上
- 乗車定員:5人以上
一見サイズがそこまで大きくないように見える車であっても、排気量が大きいとボディサイズに関係なく3ナンバーに分類されます。なかには、同じ車種でもグレードによって分類されるナンバーが異なるケースもあるため、事前によく調べておくことが重要です。
5ナンバーと3ナンバーの税金の違い
車両のサイズや排気量の違いによって、5ナンバー(軽自動車)と3ナンバー(普通車)では納める金額が異なります。とくに、自動車税(軽自動車税)と自動車重量税では大きな差が出ます。それぞれ、詳しく紹介します。
自動車税・軽自動車税
軽自動車税には「軽自動車税」が課され、普通車には「自動車税」が課されます。どちらも毎年4月1日時点で車を所有している方を対象に、1年間分の納付義務が発生するもので、支払いのタイミングや納期などに大きな違いはありません。
| ナンバー区分 | 年間税額 |
| 5ナンバー(軽自動車) | 10,800円 |
| 3ナンバー(普通車) | 39,500~58,000円 (排気量による) |
3ナンバー(普通車)は車種やグレードによって排気量が異なり、排気量が多いほど自動車税は高額になります。軽自動車の排気量は一律で定められているため、自動車税も一律です。
なお、普通車も軽自動車も新車登録がされてから13年以降は税額が加算されるため、気を付けましょう。
自動車重量税
自動車重量税は車検のタイミングで収める税金で、車両重量によって税額が決められます。
| ナンバー区分 | 重量税(2年) |
| 5ナンバー(軽自動車) | 6,600円 |
| 3ナンバー(普通車:~1.5t) | 24,600円 |
3ナンバーは重量に応じて段階的に増加しますが、軽自動車は一律料金です。このため、車体が大きくなりがちな3ナンバーは税金面で不利になる傾向があります。
車検頻度の違い
5ナンバーと3ナンバーでは、車検の頻度に違いはありません。いずれも以下のスケジュールです。
| 初回車検 | 新車登録から3年後 |
| 以降の車検 |
2年ごと |
ただし、車検費用には差があります。3ナンバーは重量税や整備項目が多くなるため、総費用が5万~10万円になることもあります。軽自動車(5ナンバー)の場合、一般的に4万~7万円程度で済むため、維持費の面でも軽自動車がコストを抑えられます。
軽自動車の5ナンバーのメリット・デメリット

軽自動車の5ナンバーには、経済性や運転のしやすさなど多くのメリットがあります。一方で、装備や積載性などの面では制約もあります。
ここからは、実際に5ナンバー軽自動車を所有する際のメリットやデメリットをそれぞれ具体的に整理します。
・5ナンバーのメリット
・5ナンバーのデメリット
5ナンバーのメリット
軽自動車の5ナンバーには、以下のようなメリットがあります。
- 維持費が安い:軽自動車税、自動車重量税、保険料が普通車に比べて安価。
- 燃費性能が高い:排気量が小さくエンジン効率が高いため、燃費が良い。
- 小回りが利く:全幅が1.48m以下なので狭い道や駐車場での取り回しが容易。
- 価格が手ごろ:新車価格が100万円前後から購入可能。
- 登録手続きが簡素:車庫証明の取得が不要な自治体も多く、登録も簡単。
これらの特徴から、普段使いや初めてのマイカーとして非常に人気があります。
5ナンバーのデメリット
一方で、5ナンバーの軽自動車には以下のようなデメリットも存在します。
- パワー不足:660ccの排気量では加速や高速走行時に物足りなさを感じることがある。
- 定員が4名まで:普通車と比べると乗用人数が制限される。
- 積載性に限界がある:トランクや荷室スペースが狭く、大型の荷物を運びにくい。
- 安全性能・装備が限定的:車両重量やサイズ制限によって搭載できる安全装備や快適装備が制限される場合がある。
使用目的や家族構成によっては、普通車やミニバンなどを選択した方が適していることもあります。
軽自動車のナンバープレートは変更できる?
軽自動車のナンバープレートは、一定の条件下で変更が可能です。引っ越しなどによる登録住所の変更、名義変更、新車購入時などにナンバープレートの番号や色を変更することができます。
ここからは、ナンバー変更の手続きと選択肢を紹介します。
・変更は可能
・黒ナンバーや白ナンバーにも変更できる
変更は可能
ナンバープレートの変更は、以下のケースで行えます。
- 住所変更(転居)
- 名義変更(譲渡・相続)
- 番号変更(希望番号制度を利用)
希望番号制度を利用すれば、特定の数字(例:「8888」や「1234」など)を指定することの可能です。
変更手続きは運輸支局や軽自動車検査協会で行い、「車検証」「申請書類」「印鑑」などが必要です。番号変更に関しては、全国自動車標板協議会のサイトを通じてオンライン予約もできます
黒ナンバーや白ナンバーにも変更できる
軽自動車のナンバープレートは、用途に応じて「黒ナンバー」や「白ナンバー」に変更することも可能です。
| 黒ナンバー (営業用軽貨物) |
・軽貨物で運送業などの届け出をすれば黒ナンバーに変更可能。 |
| 白ナンバー (記念版など特別仕様) |
・過去には「ラグビーワールドカップ記念ナンバー」「東京オリンピック記念ナンバー」など白色プレートが交付された。 ・寄付金を支払うことでデザインナンバーが選べることもある。 |
2025年現在では、「大阪・関西万博特別仕様ナンバープレート」を選ぶことで軽自動車でも白色のナンバープレートの装着ができます。
軽自動車の5ナンバーに関するご相談は軽の森へ!
軽自動車の5ナンバーは、日常使いに最適な乗用車区分として、多くのユーザーに選ばれています。税金や維持費が抑えられるだけでなく、運転のしやすさや取り回しの良さなど、多くのメリットがあります。ただし、積載量や装備面での制約もあるため、用途に応じた車種選びが重要です。
軽の森では、5ナンバー軽自動車の購入・登録から、ナンバープレートの変更、名義変更までをトータルサポートしています。豊富な車種と専門知識を持つスタッフが、お客様1人ひとりのニーズに合わせた最適なご提案をいたします。
軽自動車に関する疑問や手続きについて、お悩みの方はぜひお気軽にご相談ください。
皆さまからのお問い合わせ・ご予約を心よりお待ちしております。